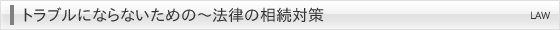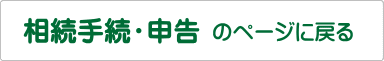今回は相談事例を通じて、法定遺言事項と付言についてご紹介します。
私には妻と二人の子A、B、が、そしてAには子(私の孫)もおり、そろそろ遺言書を書いてみようと思います。遺言書には財産の分け方を書くものと聞きましたが、それ以外に、次のようなことを書いてよいのでしょうか?
- ① 孫の教育資金として、預貯金の一部を渡したいと考えています。遺言で法定相続人以外にも財産を渡すことができるのでしょうか。
- ② 現状、家族間の仲は良好ですが、この遺言によって関係が悪くならないか心配です。孫へ財産を渡す理由とともに、家族への感謝の気持ちを遺言に書くことはできるのでしょうか。
どちらも遺言書に書くことは可能です。特に、遺言書の内容によりトラブルが起きそうなときは、②を添えることで、遺言の意図を補う大切なひと工夫になります。
 ご相談の①は、要件を満たした遺言書に書くことで、法的な効力を持つと法律で定められている事項である法定遺言事項になります。また、遺言で相続人以外の方へ財産を渡すことを遺贈といい、孫等の法定相続人以外の方にも特定遺贈として財産を渡すことができます。
ご相談の①は、要件を満たした遺言書に書くことで、法的な効力を持つと法律で定められている事項である法定遺言事項になります。また、遺言で相続人以外の方へ財産を渡すことを遺贈といい、孫等の法定相続人以外の方にも特定遺贈として財産を渡すことができます。
法定遺言事項には、身分関係として遺言認知(民法781条2項)、未成年後見人の指定(民法839条)、推定相続人の遺言廃除・取消し(民法893条、894条)等があります。
財産に関する事項として、祭祀主宰者の指定(民法897条1項)、相続分の指定・指定の委託(民法902条)、遺贈(民法964条)等があります。
遺言の執行に関する事項として、遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)があります。
ご相談の②は、法定遺言事項ではありませんが、「付言」という形で、亡くなる方の思いやメッセージを自由に書くことができます。
例えば、「孫には勉強を頑張ってほしいので、少しばかり財産を渡します。家族みんなに感謝していますし、どうかこの遺言を尊重して、争いなく過ごしてほしいと願っています。」といった形で記載するとよいでしょう。
「付言」は法定遺言事項ではなく、このような文章に法的な効力はありませんが、遺族の心に届く大切なメッセージになります。遺産分割のトラブルを防ぐためにも、付言はとても有効です。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 成年後見制度とは2025/12/20
- 相続等により取得した活用見込みのない土地の処分方法2025/11/20
- 認知症の疑いがある方でも遺言作成は可能か2025/10/20
- 高齢の親の財産を子が管理するための留意点2025/09/20
- 死後離縁2025/08/20
- 数次相続2025/07/20
- 死後認知2025/06/20
- 遺言書の封印を解く前に知っておくべき手続き2025/05/20
- 相続登記時に申出が義務化される生年月日等2025/04/20
- 米国に相続財産があり国籍の確認が必要な場合の相続手続き2025/03/20
- 相続された事業用負債の保証2025/02/20